スミマサノリ「月曜日にオジャマシマス」
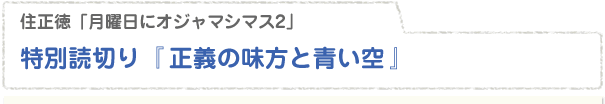
|
「別の人にまわしてくれる?」 プツンッと音を立てて電話が切れた。ツーツーツー。これで5回目のコールチェンジだ。どうやら僕には向いていないらしい。昨日はテレクラで2人ゲットしたぜうひひひ。同僚の言葉にそそのかされてやって来たが、現実はそう簡単ではなかった。何を話したらいいのか見当もつかない。2時間分の料金を払っていたのでまだ1時間も残っている。もったいないが仕方ない。きっと残りの1時間だって同じ事の繰り返しだ。ここを切り上げて仕事に戻らないといけない。重い気持ちで身支度を整えていると、隣りの部屋から年輩の男性の声が漏れ聞こえてきた。 「おっちゃん、正義の味方やねん」 正義の味方? ここのところ、何をやってもうまくいかない。仕事もプライベートも八方ふさがり。そう、最近の僕は追いつめられていた。これから仕事に戻ったところで上手くいかない事は分かってる。そんな時に聞こえてきた「正義の味方」。反射的に壁を蹴り上げそうになった。何が正義の味方だ。軸足に重心を置いて壁に狙いを定める。これでもくらえ。 「困った事があったらおっちゃんに相談せえや」 あ、………。 再び男性の声を聞いた瞬間、一気に15年前の記憶が蘇ってきた。 15年前の秋、僕は病院のベッドの上にいた。  |

大学4年の夏、僕は大けがをして6ヶ月間入院した。交通事故だった。病院に担ぎ込まれた時、僕は生死の境をさまよっていたらしい。バイクでトラックに突っ込み、大きく空を飛んだ。メット越しに見た空がやけに青かったのを覚えている。というか、それしか覚えていない。再び意識が戻った時、僕は病院の白い壁を見上げていた。手術から1ヶ月が経っていた。1ヶ月間、集中治療室で眠っていたらしい。 目が覚めてからは順調に回復に向かい、集中治療室から6人部屋に移された。1番奥の窓側のベッドだった。腰と首の骨を折っていたので、6人部屋に移ってからもしばらくは寝返りすらうてない状況だった。窓からは空しか見えず、空を見ると事故の事を思い出すのでいつもカーテンを閉めてもらっていた。 僕の左隣りには僕と同じように身動きの出来ない男性が寝ているようで、カーテン越しに低いうめき声が聞こえた。うううう。初めはそのうめき声が耳障りで仕方なかった。部屋を変えてもらおうと思っていたが、うめき声とうめき声の間に妙な独り言を言っているのが分かり、次第に僕はその独り言を楽しむようになっていった。 「おっちゃんは、正義の味方やねん」 「早う良くならんと、みんな悲しむねん」 「もう行かな、もう行かな」 痛み止めが強いのだろう。神経がおかしくなっているに違いない。僕を見舞いに来た友人におっちゃんの独り言の事を教え、みんなで耳をそばだてた。 「おっちゃん、正義の味方やねん」 僕は友人たちと声を殺して笑った。な、な、あいつコレだから。と僕は自分の頭の上で人差し指をくるくる回した。 |

| 病院生活が3ヶ月も過ぎると、友人たちはすっかり顔を見せなくなった。卒業旅行があるだとか、就職の準備が忙しいだとか、みんなそれらしい理由をつけて自分たちの日常に戻っていった。僕の日常は相変わらずベッドの上だ。あと少しすれば立てるようになるから、そうしたらリハビリを始めましょう。医者は同じ台詞を繰り返し、気付けば3ヶ月も寝たきり状態が続いた。もしかしたらずっとこのままなのかもしれない。カーテンはずっと閉じたままだった。 |

「おっちゃんな、正義の味方やねん」 ある日、おっちゃんはいつもより大きな声でそう言った。おっちゃんの独り言にも飽きていたので、僕はうんざりとして目を閉じた。寝てしまおう。 「なあ、なあ、聞こえるか?」 どうやら、おっちゃんは僕に話しかけているようだった。面倒臭い。 「なあ、ぼっちゃん。ぼっちゃんは治るから大丈夫やで」 「……」 「おっちゃんには分かんねん」 どんどん声が大きくなっていく。他のベッドの患者たちにも聞こえているに違いない。無視を続ける訳にもいかず、おっちゃんの声に答える事にした。 「いや、僕の状態はあまり良くないみたいです」 「何言ってんねん。おっちゃんには分かんねんって」 なんだこいつ。ボソボソと独り言を繰り返すような奴に何が分かるというのか。気休めだったとしたらとんだ悪趣味だ。 「へえー、正義の味方って凄いんですね。何でも分かるんだ」 出来る限り慇懃無礼に接して、おっちゃんを貶めてやろうと思った。 「ああ、分かるで」 「じゃあ、僕が何で入院したか、分かりますか?」 「ああ、もちろん。あれはひどい事故やったなあ。バイクが100メートルはぶっ飛んでたで」 「まるで事故を見たかのような口ぶりだ」 「見たって言うか、おっちゃんがぼっちゃんを助けたんやからなあ。おっちゃんがいなかったら、ぼっちゃん死んでたで」 「まさか、だってあなたは1年以上もそうやってベッドの上でしょ。いい加減な事を!」 思わず声を荒げてしまった。もし身動きが取れる体だったらおっちゃんに詰め寄って殴っていたかもしれない。 「ほんまやって。おっちゃんは正義の味方やから何でも出来んねん」 「フンッ!だったら自分の体を治したらどうですか?」 「それはでけへん。正義は人様の為に使うもんや。我が身の為に使う事はでけへん」 「ああ、そうですか。だったら俺の為に、その正義ってやつを使って下さいよ」 「だから、おっちゃんが助けたって言うたやん」 「俺を元の体に戻せって言ってんですよ」 「ああ、それだったら大丈夫や。じき良くなる」 「いますぐ治せ」 「いますぐは無理やなあ」 「ほら見ろ、この嘘つき」 「嘘やあらへん」 「フンッ!」 「困った事があったらおっちゃんに相談せえや」 「うるさい!」 看護婦さんが検温に入ってきて、僕の気持ちはおさまった。半分ボケたおっちゃんの戯言だ。熱くなった事を反省した。 |

|
年末になって、おっちゃんの容態は急変した。集中治療室に運ばれた、という所までは聞いていたがその後の事は聞かなかった。結局、顔も知らないまま、正義の味方のおっちゃんとはそれっきりであった。 僕はリハビリも順調に進み年明けには退院出来る見込みであった。大学を1年留年する事に決めた。決まっていた就職先も事故のせいでダメになっていた。退院したら再び就職活動をしなければならない。久しぶりに開けたカーテンからは、事故の時と同じ青い空が見えた。 |

|
そして今、僕は小さな広告代理店で営業職に就いている。入社から15年、特に目立った活躍もなく、営業途中に窓のないテレクラで打ちひしがれていたりする。 「おっちゃん、正義の味方やねん」 この声はあのおっちゃんに違いない。懐かしさがこみ上げてきた。衝動に任せて壁をドンドン叩き、壁越しに声をかけた。 「おっちゃん、僕です。分かりますか?」 「……」 壁の向こうから沈黙が伝わってきた。 「ほら、15年前、おっちゃんの横のベッドで」 「……」 「ああ、懐かしいなあ、覚えてますか?」 「……、ちょっと切るわ、……すまんのう」 「おっちゃん! 無事だったんですね? ああ、こんな偶然があるなんて」 「こらっ! うるさいぞ!」 「15年前、昭和病院に入院してた、交通事故の、ほら」 「交通事故? なんやねん、それ?」 「おっちゃん、集中治療室に行ったって聞いてたから、もうダメなのかと」 「だから、なんやって! ええ加減にせえよ」 「だって、正義の味方のおっちゃんでしょ?」 「……」 「やっぱり、そうだ。その節は本当に…」 「お前のせいでさっきのコール逃したやんけ」 「コールなんてどうでもいいじゃないですか。あのとき、なんだかんだ言っておっちゃんに励まされたんです。お陰で体も元に戻って無事に就職も出来て」 「ああ、そうか。それは良かったな」 「だから、顔を見てお礼を言いたいって言うか。そっち行ってもいいですか?」 プルルルル 「ちょ、ちょっと待てや。コールが来たから、こっちが先や」 「分かりました。じゃあ、大丈夫になったら教えてください」 「……、おっちゃん正義の味方やね……、ほう、……、ふんふん……」 正義の味方のおっちゃんはボソボソと電話口の女性と会話を始めた。 ああ、何て偶然なのだろう。勢いに任せておっちゃんに告げた言葉に嘘はなかった。僕はあの時、おっちゃんから勇気をもらっていたのだ。もしかしたら、おっちゃんは本当に正義の味方なのかもしれない。僕の人生の転機に現れては僕を正しい方向に導いてくれる。事故から15年、漫然とした日々を送る僕に再び勇気をくれるためにやって来てくれたのだ。 プルルル。 僕の部屋の電話が鳴った。慌てて取ると、隣りのおっちゃんからだった。 「おい、正義の味方のおっちゃんや」 「おっちゃん! 隣りに行ってもいいんですか?」 「あかん。これから、お前を救ってやる」 「え? どういう事ですか?」 「おっちゃんが今話をつけてやったから、これからまわす女と話すといい」 「え? いいんですか?」 「ああ、言ったやろ。困った事があったらおっちゃんに相談せえ、って」 「でも、そんな、悪いですよ」 「ええねん、これで、お前の人生も変わるぞ」 「お、おっちゃん……」 おっちゃんはやっぱり僕の正義の味方だった。 当時、友人たちと笑い者にしたりして本当に申し訳なかった。あの頃の僕は、何と言うかこう、反抗期みたいな時期だったのだ。今ならおっちゃんの好意を信じられる。 おっちゃんから回ってきた電話に出た。 「もしもし…?」 「ああ、アンタなの? 今から会えるって人は」 「ええ、ま、まあ」 「しかし、アンタも変わり者だねえ、59才の私を抱きたいなんて」 59才と言えば、アレだ。僕の母親と同じ年だ。 (2007/10/29 住正徳) |